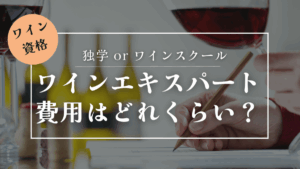ワインエキスパート資格試験の合格率は?難易度や取得メリットを合格者が解説!
 ぴのこ
ぴのこワインエキスパートの資格試験に挑戦しようと思うんですけど、合格率や難易度はどれくらいなんですか?
 きむ
きむワインエキスパートかぁ、懐かしいな。僕も大学生(21歳)の時にチャレンジして合格したよ。
 しょうさん
しょうさんぴのこさんの挑戦を応援しますよ!それでは、ワインエキスパートの合格率や難易度、試験内容などを見ていきましょう。取得メリットについてもお伝えします!
ワインエキスパートとは
ワインエキスパートとは、一般社団法人日本ソムリエ協会(以下、ソムリエ協会)が認定する資格です。ソムリエ協会のHPでは、以下のように定義されています。
ワインエキスパートとは酒類、飲料、食全般の専門的知識・テイスティング能力を有する者を言う。 プロフェッショナルな資格ではないので職業は問わず、むしろ愛好家が主な対象となる。
一般社団法人 日本ソムリエ協会
 きむ
きむワインエキスパートは、1996年から認定が開始された資格だね。それまでは飲食業に従事するプロ向けのソムリエ資格しか無かったから、「一般の愛好家向けにソムリエと同等資格を設けてほしい」という要望に応えて生まれたというわけ。
 しょうさん
しょうさんソムリエ資格を取るには、飲食店での3年間の実務経験(ソムリエ協会員は2年)が必要になりますが、ワインエキスパートは不要です。20歳以上の成人であれば誰でも取得できるのが、ワインエキスパート資格です。
ワインエキスパートの合格率
ワインエキスパートの直近5年の合格率は以下の通りです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 3,381人 | 1,399人 | 41,4% |
| 2023年 | 3,499人 | 1,465人 | 41,9% |
| 2022年 | 3,496人 | 1,143人 | 32.9% |
| 2021年 | 3,490人 | 1,421人 | 40.7% |
| 2020年 | 3,213人 | 1,390人 | 43.3% |
| 平均合格率 40% |
 ぴのこ
ぴのこ平均合格率は40%かぁ…。なかなか狭き門ね。
 きむ
きむ日本には色々なお酒関連の資格があるけど、その中でもワインエキスパートは難しいほうだと言えるね。参考までに、他のお酒関連の資格の合格率と比較してみようか。
| 資格 | 合格率 | 主催団体 |
|---|---|---|
| ソムリエ | 32.5% | 日本ソムリエ協会 |
| ワインエキスパート | 40% | 日本ソムリエ協会 |
| ウイスキーエキスパート | 50〜60% | ウイスキー文化研究所 |
| HBA バーテンダー | 60% | 日本ホテルバーメンズ協会 |
| NBA バーテンダー | 60% | 日本バーテンダー協会 |
| 焼酎コンシェルジュ | 70% | 日本インストラクター技術協会 |
| 唎酒師 | 84% | 日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会 |
| ビアテイスター | 85% | クラフトビア・アソシエーション |
| ラムコンシェルジュ | 95%以上 | 日本ラム協会 |
| テキーラマエストロ | ほぼ100% | 日本テキーラ協会 |
 しょうさん
しょうさんソムリエやワインエキスパートなど、ワイン関連の資格の合格率が低いのは、他の資格と比べて「覚えることが多いうえに広範囲に渡る」の一言に尽きると思います。
ワインエキスパートの難易度
前項の比較表を見ていただいて分かる通り、ワインエキスパートの難易度はやや高めと言えます。
一般愛好家向けの資格とはいえ、プロ向けのソムリエ試験と覚える内容や出題範囲は変わりません。ワインエキスパート試験に合格するためには、日本ソムリエ協会が出版しているテキスト「ソムリエ教本」の内容を全て覚える必要があります。
また、他の資格試験に比べて、ワインエキスパートは覚える内容が多岐に渡ります。ワインの知識だけでも十分多いのに、他の酒類・飲料・料理・チーズ・料理とワインの組み合わせなど、ワイン以外の様々な知識も身につける必要があります。
「日頃からワイン雑誌を読んだり、ワインを飲んで慣れ親しんでいる」くらいでは、到底合格できません。ソムリエ教本に書いてある専門的な知識を丸暗記しなければ、合格は難しいと言えるでしょう。
 きむ
きむ僕が大学生時代に合格したときは独学だったし、今ほど情報も無かったからね。みっちり半年間、1日に4〜5時間ほど勉強して挑んだなぁ。それでもギリギリ間に合ったって感じだったかな…。
 しょうさん
しょうさん社会人で仕事をしながら合格を目指すとなると、そこまで多くの勉強時間は取れないでしょう。独学であれば、1年ほどかけてじっくり取り組む必要がありますね。ワインスクールに通って効率的に勉強すれば、半年くらいでもいけます。
ワインエキスパート資格試験の内容

ワインエキスパート試験は、一次試験と二次試験に分かれています。二次試験に進むためには、一次試験を突破しなければなりません。
一次試験 〜筆記〜
一次試験は筆記試験です。筆記と言っても、すべてマークシート方式(選択式)です。世界のワインに知識やその他の酒類、チーズ、料理など、すべて公式テキストの「ソムリエ教本」から出題されます。
 きむ
きむ一次試験は、1ヶ月間ほどの日程の中から自分の好きな試験日を予約して、会場でPCで解答入力→その場で合否結果が分かるよ。僕らの頃は、決まった試験日に会場へ行って鉛筆でマークシートを塗りつぶしてたから、時代は変わったね。
二次試験 〜テイスティング〜
二次試験は、スティルワイン(=非発泡性ワイン)4種類・その他のアルコール飲料1種類、計5種類のブラインドテイスティングです。ブラインドテイスティングとは、銘柄などが一切分からない状態でそのワインの特徴・素性を当てにいくテイスティングです。
スティルワインについては、外観・香り・味わいに関する表現を選択肢から選び、ワインのコメントを完成させる方式です。そして、そのワインの生産国・ブドウ品種・ヴィンテージなども選択肢から選びます。
その他のアルコール飲料については、選択肢の中から銘柄を選ぶ形です。
これらも、「普段からワインやお酒をよく飲んでいる」程度では正解できません。専門的なテイスティングスキルが求められるうえに、ワイン以外のお酒についても味を把握している必要があります。
 きむ
きむその他のアルコール飲料では、酒精強化ワインや蒸留酒、リキュールなどが出題されることもあるよ。過去には、テキーラやグラッパが出題されたり、リキュールだと「ガリアーノ」や「ベネディクティン」が出されたこともあるよ。
 ぴのこ
ぴのこワインだけを飲んでたら良いってわけじゃないのね…。頑張らなくちゃ!
ワインエキスパート資格を取得するメリット
なかなか難易度が高いワインエキスパートですが、愛好家の方が資格を取得するメリットはたくさんあります。ワインエキスパートを取得するメリットとしては、以下の7つが挙げられます。
- 世界のワインの知識が体系的に身につけられる
- ワインの楽しみ方の幅が広がる
- テイスティング技術が身につく
- 日本ソムリエ協会の認定講師になれる
- 日本ソムリエ協会主催のコンクールに挑戦できる
- 飲食業界への就職・転職時に役立つ
- 自信が得られる
①世界のワインの知識が体系的に身につけられる
ワインエキスパートの試験勉強を通じて、ワインの知識が体系的に身につきます。
ワイン愛好家の方でも、プロ顔負けの「知識」と「ワインを飲んだ経験」がある方はたくさんいらっしゃいます。ただ、その方々の知識は断片的・限定的であることが多いです。
例えば、
(ワインの銘柄はたくさん知っているけど、ワインにはどんな種類があってどのように造られているかなどは全く知らない)
(フランス・ブルゴーニュ地方のワインだけはマニアックなほど詳しいが、他の国・地域のワインは知らない)
など、「点の知識」である場合がほとんどです。
資格の勉強では、ワインの歴史や造り方、種類、ブドウ品種、世界のワイン産地などを体系的に学べます。それまで「点」の知識だったものが「線」になり、「球体」になっていくイメージと言えば良いでしょうか。
ワインに関して幅広い知識をまんべんなく身につけられることは、ワインエキスパートを取得する大きなメリットだと言えます。
②ワインの楽しみ方の幅が広がる
ワインの知識を体系的に身につけることによって、ワインの楽しみ方の幅が広がります。
これまでなんとなく飲んでいたワインも、産地やブドウ品種の特徴を知ったうえで飲めば、何倍も美味しく感じられます。また、料理とワインの合わせ方の理論も身につくので、レストランなどでは相性(=マリアージュ)を意識したワインのチョイスができるようになります。
友人たちとワインを飲む場面でも、ワインエキスパートの知識を生かしてワインを選んであげれば、きっと喜ばれることでしょう。

③テイスティング技術が身につく
ワインエキスパート試験の勉強を通して、基本のテイスティング技術が身につけられます。
テイスティング技術があれば、ワインの味・香りの特徴を的確に捉えることができます。そうなれば、ワインが格段に美味しく感じられるようになるでしょう。
また、テイスティングによってワインの品質が判断できるようになります。価格に対して品質が見合っているかどうかを正しく判断し、コスパの良いワインが見つけられるようにもなるでしょう。
また、テイスティングによってひとつのワインを深く考察できるため、ワイン愛好家やプロのソムリエたちとワインについて深く語り合えるようにもなります。
④日本ソムリエ協会の認定講師になれる
ワインエキスパート資格があれば、日本ソムリエ協会が主催する初心者向けのワイン資格「ワイン検定」の認定講師になれます。
認定講師になるための教育プログラムを修了すれば、自分で会場を押さえてワイン検定の事前講習と認定試験を実施できます。せっかく取得した資格ですから、このように活かすのも良いでしょう。
⑤日本ソムリエ協会主催のコンクールに挑戦できる
日本ソムリエ協会では3年に1度、ワインエキスパート資格保有者向けに「全日本 J.S.A ワインエキスパートコンクール」を開催しています。
優勝者には、海外研修への招待や協賛企業からワインなどの副賞が贈られます。
ワインエキスパートの取得を通して得た知識・スキルを活かして、コンクールで腕試しをしてみるのも面白いのではないでしょうか。
⑥飲食業界への就職・転職時に役立つ

これから飲食業界へ就職・転職を考えているなら、ワインエキスパートの資格があれば非常に有利です。
「ワインエキスパート=ワインの専門知識がある人材」と認められます。ワインエキスパートの資格があれば、レストランやバーなど、あらゆる飲食店において重宝されるでしょう。
加えて、ワインエキスパートの資格は、「目標達成のために努力できる人材」であることの証明でもあります。これは、採用する側からしても非常に魅力的だと言えるでしょう。
また、ソムリエを目指しているものの実務経験が足りないため、先にワインエキスパートを取得しておく人もいるようです。
【当サイト運営者の経験談】
私は大学生時代にワインエキスパートを取得し、それを強みにして面接へ臨み、ホテルへ就職できました。面接では、ワインエキスパートの資格をもっていることが非常に高く評価されたと記憶しています。
就職して1年後、まだソムリエ資格をもっていなかったものの、ワインエキスパート資格はあるということで上司のソムリエから認められ、ホテル内のフレンチレストランへ最年少のソムリエ見習いとして配属されました。
どちらも、ワインエキスパートの資格が有利に働いて実現できたことです。
⑦自信・達成感が得られる
ワインエキスパートを取得するためには、それなりにしっかりと勉強しなければなりません。ワイン業界に従事していない方にとっては未知の領域へのチャレンジなので、かなり難しく感じるはずです。
そんな困難を乗り越えて合格できれば、自身・達成感が得られます。頑張った自分を褒めてあげたくなること間違いなしです。
年齢を重ねると、何かに挑戦して目標達成する経験というのは、若い頃に比べて少しずつ減ってきます。ワインエキスパートに挑戦して得られる達成感は、きっと素晴らしい経験になるでしょう。
2025年の試験開催日
 しょうさん
しょうさん最後に、2025年のワインエキスパート試験開催日を確認しておきましょう。
| 試験 | 開催日 | 備考 |
|---|---|---|
| 一次試験 | 2025年 7/15(火)〜8/25(火) | ・左記の日程内で、自身が予約した日に受験 ・受験票は無し、指定の身分証明書が必要 ・試験はCBT方式(※) ・試験終了後、パソコン画面上で合格発表 |
| 二次試験 | 2025年 10/6(月) | ・受験票は9月中旬頃から順次発送 ・合格発表は10月下旬頃 |
(※)CBT方式=コンピューターを利用して解答する試験方式。受験者はパソコンに表示された試験問題に対して、マウスやキーボードを用いて解答します。事前に各自受験日時・会場の予約が必要です。
2025年のワインエキスパート試験の出願期間は、2025年3月3日㈪10時 ~ 7月10日㈭17時59分まで
受験資格などについての詳細は、日本ソムリエ協会の募集要項をご確認ください。
まとめ
ワインエキスパート資格の合格率は40%ほどで、難易度はかなり高いと言えます。
しかし、取得することでワインの楽しみ方・美味しさは何倍にもなりますし、将来的に飲食業界へ転職することがあれば強力な武器にもなります。ソムリエの立場からも、ワイン愛好家の方々がワインエキスパートを取得して損はないと断言できます。資格取得を考えている方は、ぜひチャレンジしてみてください。
独学の場合は一日2〜3時間、1年ほどかけて準備する必要があります。もっと効率的に短期間で取得したいという方は、ワインスクールの受講がおすすめです。