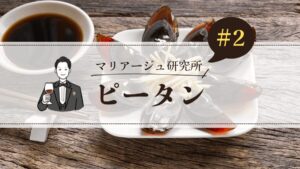【マリアージュ研究③】ジビエの王様「山シギ(べキャス)」とワイン
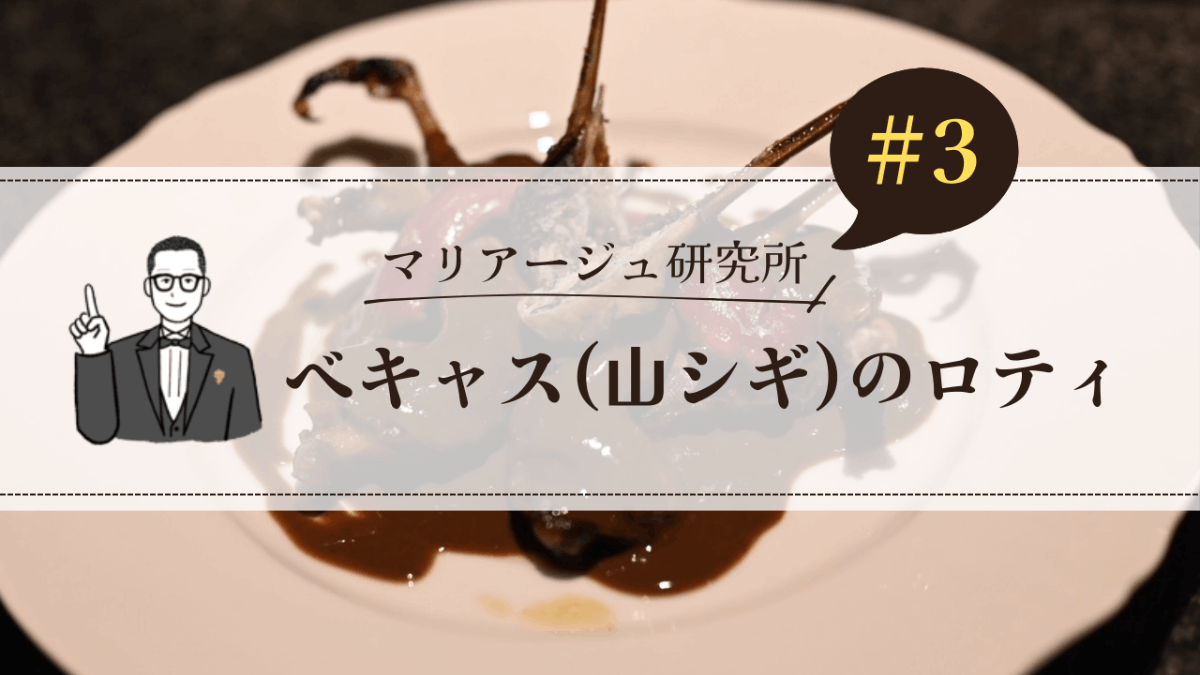
今回は、山シギ(べキャス)とワインのマリアージュ研究です。
少し前の話になります。2024年10月頃、仕事仲間のカルロスさんと、今年は何のジビエを食べようかと相談していたところ、(べキャスはどうでしょう?)となりました。
カルロスさんはべキャス未経験、私も1回しか食べたことがなかったため(それはぜひ!)となり、京都・祇園のフレンチ「祇をん尚」に(入荷したら連絡ください)と伝えて待つこと数ヶ月。2025年1月末に入荷の連絡をいただいたので、食べに行ってきました。
そこでは、私のソムリエ人生で経験したことのない素晴らしいマリアージュが待っていました。
ジビエの王様【山シギ(べキャス)】とは

山シギはチドリ目シギ科の鳥類で、フランス語ではBecasse(べキャス)と言います。この記事内では、表記をべキャスで統一します。
体長は35cmほどで、ずんぐりむっくりした体型と長いクチバシが特徴です。体型に似つかわしくないシャープなこのクチバシを地面の中まで刺し込んで、地中の昆虫を捕食します。
べキャスは、夏にはユーラシア大陸の中緯度で繁殖し、冬はヨーロッパ・アフリカの地中海沿岸・東南アジアなどに渡って越冬します。日本においては、本州中部地方より北の伊豆諸島あたりで繁殖し、冬は温暖な地方に移動するとされています。
狩猟で得られる野生鳥獣(=ジビエ)の一種で、中でもべキャスは「ジビエの王様」と称されるトップ・オブ・トップのジビエです。
ジビエの王様と称される理由
べキャスがジビエの王様とされる理由は、まず第一に味わいの素晴らしさゆえでしょう。
鳥類のジビエには、ウズラ・ツグミ・鴨・鳩・キジ・雷鳥などいろいろありますが、べキャスには他の鳥類とは一線を画す旨味と滋味があります。
第二の理由は、その希少性ゆえです。
べキャスは狩猟が難しい鳥類です。夜行性でなかなか人目に付かず、見つけることができたとしても変則的に動き回るので狙いが定めにくいうえに、脳みそまで美味しく食べられるよう首部分に的を絞って確実に仕留めなければなりません。
熟練の猟師でなければ仕留めるのが非常に難しいため、流通量が他のジビエに比べて極端に少ないのです。
さらに、フランスでは過去の乱獲によってべキャスが禁猟となっており、現在はスコットランド産しか輸入されていません。そのような背景もあり、フレンチの料理人であってもべキャスの調理経験がない人は多いです。ソムリエでも、食べたことがない人の方が多いのではないでしょうか。
べキャスの価格
希少価値が高いべキャスは、価格も当然に高いです。
レストランにもよりますが、スコットランド産1羽で10,000円〜15,000円はするでしょう。稀に国産のべキャスも入るようですが、国産べキャスの価格はスコットランド産の約3倍ほどです。
そうそう気軽に食べられるジビエではないため、食べる方も気合いを入れて食べなければなりません。
べキャスの食べ方(調理法)
べキャスは、シンプルなローストや肉部分だけを使ったパイ包み焼きなど、様々な食べ方があります。
もちろん肉自体も美味しいのですが、べキャスの価値は肉よりも内臓にあります。そのため、ローストしたべキャスに内臓を使ったソース(=ソースサルミ)で食べるのが最も美味しいとされています。
べキャスをはじめとしたジビエは、少し熟成させる方が美味しくなります。ただ、べキャスの場合はソースに内臓を使うので、料理人が熟成度合いを見誤るとソースが臭くなってしまいます。私もかつて働いていたフレンチレストランでべキャスを提供したことは何度かありましたが、一度だけ耐え難いほどの強烈な匂いを発していたことがありました。
なかなか難易度が高いべキャスの内臓ソースですが、祇をん尚のシェフはべキャスの調理経験も豊富で、以前にカルガモを食べさせてもらった経験からジビエ料理は得意分野ということも知っていたので、安心してお任せすることにしました。
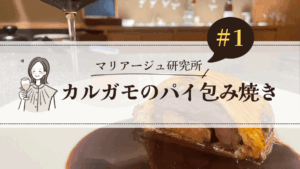
祇をん尚のパーフェクトな【べキャスのロティ ソースサルミ】
今回、祇をん尚のシェフからは(入荷3日以内に来店してください、それ超えるとソースサルミは難しくなります)と言われていました。しかも、入荷するまではべキャスの状態が分からないため、入荷時の状態次第ではソースサルミができるか分からないとのこと。
加えて、いつ入荷するか分からない中で、入荷連絡から3日以内に都合をつけて行く必要がありました。美味しいべキャスを食べるには、いくつもハードルを越えなければならなかったのです。
幸いなことに入荷時の状態は良好であり、連絡をもらってから3日以内に予定も空けられたので、なんとかべキャスにありつくことができました。

肉質はしっかりしていて、適度な野性味もあり、噛むほどに旨味が溢れてきます。そして、べキャスの脳みそはトロリとして濃厚、独特の風味があります。
特筆すべきは、ソースサルミの完成度!臭みが全くなく、内臓の旨味と心地よい風味だけを上手に引き出したパーフェクトなソースでした。
以前から、祇をん尚シェフのソースが美味しいことは知っていましたが、今回のソースサルミには敬服いたしました。
非常に滋味深い味わい。野生の命をいただき、それが自身の生命力となっていくのを感じます。時々ガリッと、散弾銃の弾をかじることがあります。皆さんもジビエを食べるときは、弾を誤って飲み込まないように注意してください。これもジビエの醍醐味ですね。
とにかく、大変美味しいべキャスでした。
山シギ(べキャス)とワインのマリアージュ
肝心の、べキャスとワインのマリアージュについてです。
べキャスに合うワインを考察
べキャスに合わせるワインは「祇をん尚」ソムリエの尚一郎さんにお任せしていたのですが、事前に自分なりのマリアージュを考察していました。
ポイントは、べキャスの「野性味」と「ソースサルミ」です。
一般的には、ジビエには熟成したワインを合わせることが多いです。ワインは、若いうちは果実味が全面に出ているのですが、熟成してくると干し肉などの野性味が感じられるようになります。熟成したワインの野性味とジビエの野性味をマッチさせるというわけですね。
とりわけ鳥類のジビエには、「ピノ・ノワール」というぶどうの熟成した赤ワインを合わせることが多いかと思います。これは、熟成ピノ・ノワールによく現れる野性味や、赤身肉・レバーを食べたときに感じるような「鉄っぽい風味・血の風味」が、鳥類のジビエによく合うためです。
ただ、ピノ・ノワールはどちらかと言えば繊細な風味の赤ワインです。べキャスの肉の風味にはマッチするかもしれませんが、ソースサルミの内臓の風味にはやや負けてしまうかもしれません。
そこで候補に上がってくるのが、熟成した「シラー」というブドウ品種の赤ワインです。
熟成シラーは、熟成ピノ・ノワールと同様の野性味や鉄っぽさがありながら、ピノ・ノワールよりもやや力強い香りと味わいなので、ソースサルミのクセの強さも上手く包み込んでくれる可能性が高いです。
(私が現役ソムリエなら、フランス・ローヌ地方でシラーやグルナッシュといったブドウを主体に造られる銘醸ワイン「コート・ロティ」や「エルミタージュ」、もしくは「シャトーヌフ・デュ・パプ」などの熟成ワインを合わせるかな…)など考えながら、ソムリエ尚一郎さんのワインチョイスを楽しみに待ちます。
【1本目】コート・ロティ 2000(パトリック・エ・クリストフ・ボンヌフォン)

1本目に合わせていただいたのは、フランス・ローヌ地方のコート・ロティ 2000年でした。やはり、尚一郎さんもコート・ロティを出してきましたか。
コート・ロティは「焼けた丘」という意味で、その名の通り非常に日照量が多い南東向きの急斜面で造られたブドウから生まれるワインです。ただ、その名前から想像されるような濃くて力強いワインかと言えば、そうではありません。むしろ、ブルゴーニュのピノ・ノワールに近いエレガントで繊細なワインです。
これは、ローヌ地方の北限にあるコート・ロティの地域が、その北側にあるブルゴーニュ地方に近い気候だからです。
このコート・ロティ 2000年は、24年もの熟成を経てタンニンが驚くほど滑らかになっています。ドライプラムやドライベリーなどの凝縮感がある乾いた果実味に、革やキノコ・腐葉土・タバコの葉などの枯れた熟成香がキレイに溶け合っています。
コート・ロティは熟成すると、ピノ・ノワールと間違うほどのエレガントで官能的なワインになります。このワインは少し熟成のピークを過ぎているかなと感じましたが、べキャスの肉質やサルミソースにも負けず、上手くマッチしていました。
教科書どおりのキレイなマリアージュという感じです。まだまだ想定の範囲内ですぞ、ショウイチロー殿。
【2本目】ジゴンダス 2003 (タルデュー・ローラン)

2本目は、同じくローヌ地方のジゴンダス2003年です。こちらのワインは、「グルナッシュ」というブドウを主体に、「シラー」をブレンドして造られるワインです。
グルナッシュはシラーよりもタンニンが控えめで、果実味がより前面に出る味わいのワインを生みます。加えて、先ほどのコート・ロティがローヌ地方の北部にあるのに対し、ジゴンダスは南部にあります。より温暖な気候で熟したブドウから造られるため、ジゴンダスの方がコート・ロティよりも果実の凝縮感やアルコールのボリューム感が強いです。
さらに、この2003年はヨーロッパ全土が非常に暑い年だったため、例年にも増して濃厚なワインができた年でした。
それらの背景もあって、コート・ロティと同じような熟成香はあるものの、まだまだパワフルで生き生きとした果実味 とボリューム感が感じられました。先ほどのコート・ロティはややピークを過ぎた味わいだったため、ジゴンダスの方がソースサルミのクセのある風味とはよく合っていたと思います。
ここで、ワイン愛好家の方ならお気づきかもしれませんね。そうです、ワインを出す順番が逆ではないのか?という点です。
複数のワインを飲む場合、飲む順番のセオリーは「新しい年代のワイン→古い年代のワイン」です。本来であれば、ソムリエは「ジゴンダス2003年 → コート・ロティ2000年」の順で出すべきなのですね。しかし、ソムリエ尚一郎さんは逆の順番で出してきました。
これは、コート・ロティがややピークを過ぎて優しい味わいになっており、ジゴンダスの方がまだパワフルで味が強かったことが理由でしょう。先にジゴンダスを出してしまうと、後に出されたコート・ロティを物足りなく感じてしまうため、あえて先に優しい風味のコート・ロティを出したのではないでしょうか。
このように、ソムリエのサービスにおいては、時にはセオリーを無視することが満足感や感動に繋がります。そして最後にソムリエ尚一郎さんは、見事にセオリーを無視した1本で私を感動させてくれたのです。
【3本目】ゲヴュルツトラミネール・ヘングスト・グランクリュ 2004 (ツィント・フンブレヒト)

最後の1本は、なんと白ワインでした。フランス・アルザス地方のゲヴュルツトラミネール 2004年です。これには、色々と驚かされました。
まず、ワイン自体のレアさに驚きです。よく手に入ったなと…。日本に出回っているアルザスワインは若いものが主流で、20年も熟成したものにお目にかかることはなかなかありません。また、ゲヴュルツトラミネールというブドウのワインは若いうちに飲むことが多く、私自身も熟成したものを飲む機会はほとんどありませんでした。
次に、その香りと味わいの素晴らしさに驚きました。干したアプリコットやミカンの皮、ライムリーフ、白檀のようなお香の香りも少し感じられます。長期熟成によるシェリーのような酸化のニュアンスもあります。
口に含むと、乾いた果実味がしっかりと感じられ、ブドウ由来の酸味と酸化による酸味のバランスが非常に良く、味わいの余韻も驚くほど長いです。熟成した白ワインはこれまでもたくさん飲みましたが、それらのどのワインとも違う個性が感じられます。
(ワイン自体はとても美味しいです。だからといってべキャスに合わせるのは、ちょっと奇をてらいすぎじゃないですかね〜)など言いながら半信半疑で合わせてみると、これがベストマリアージュ!
ワインと料理のマリアージュには、「料理が美味しくなる組み合わせ」「ワインが美味しくなる組み合わせ」などがあるのですが、もうひとつ上の次元にいくと「料理とワインが渾然一体となる組み合わせ」があります。
今回のべキャスと熟成ゲヴュルツトラミネールはまさにそれで、べキャスの肉の風味とソースサルミの内臓の風味、それらとワインの味が溶け合ってひとつの新しい味を創造しているのです。マリアージュの究極系と言っても過言ではありません。
これは狙ってできるレベルのものではないと思いましたので、ソムリエ尚一郎さんに(偶然でしょ?)と聞いてみたところ、以前に熟成ゲヴュルツトラミネールと肝料理のマリアージュに感動したことがあり、これならソースサルミとも合うのでは?との予想で出したとのことでした。
なるほど、さすがのマリアージュでございました。
べキャスの美味しさとアルザスワインの深さを知る
人生2回目のべキャスでしたが、とても美味しかったです、このべキャスなら、毎年食べたいと思わせてくれました。
そしてまさかまさかの、熟成したフランス・アルザスの熟成ゲヴュルツトラミネールがべキャスとベストマリアージュだなんて、、、非常に貴重な経験ができました。祇をん尚のシェフとソムリエに大感謝です。
アルザスでは、お肉料理と熟成したアルザスの白ワインを合わせるというのは聞いていたのですが、実際に合わせてみると(こんなにも合うのか!)と新たな発見がありました。
私もアルザスのワインは大好きでたくさん飲んできたのですが、改めて深さを知ることができました。私の人生でも間違いなく記憶に残るマリアージュ体験となりました。
最後に、今回飲んだワインをまとめておきます(ヴィンテージは異なります)。アルザスの白ワインは焼き鳥なんかとよく合うので、ぜひ試しみてください。